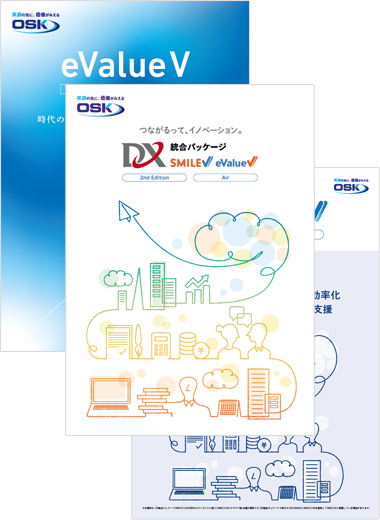知識のツボ 電子帳簿保存法 国税関係帳簿保存編

最終更新日:2024/1/12
国税関係帳簿保存
電子帳簿保存法では、国税関係帳簿書類の分類に応じて、電子データの保存方法が定められています。
ここでは、「国税関係帳簿の電子データ保存」を見てみましょう。

国税関係帳簿のデータ保存をおこなうには
国税関係帳簿の電子データ保存を行うためには、大きく分けて「対象帳簿の選定」 「システムの選定」 「事務手続きの明確化」という3つのステップがあります。
1. 対象帳簿の選定
自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成した帳簿(「仕訳帳」「総勘定元帳」「その他の帳簿」)が対象です。
主要簿の「仕訳帳」「総勘定元帳」以外の「その他の帳簿」については、どの帳簿を電子化するのかを検討しましょう。
- 「その他の帳簿」とは、法人税法施行規則の別表二十で区分され、記載事項が定められています。
2. システムの選定
国税関係帳簿データのシステム的な要件
以下のような要件を満たしているシステムを選定する必要があります。
| 訂正・削除履歴の確保 | 訂正・削除・追加を行った場合には、これらの事実およびその内容を確認することができること |
|---|---|
| 相互関連性の確保 | 関連する当該国税関係帳簿の記録事項との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと |
| 関係書類等の備付け | システムの仕様書、マニュアル、電子保存に関する事務手続きを明らかにした書類などが用意されていること |
| 見読可能性の確保 | 帳簿データをディスプレイやプリンタなどを使って整然とした形式で明瞭な状態で速やかに出力できること |
| 検索機能の確保 | 取引年月日、取引金額、取引先による検索ができること |
国税関係帳簿データ保存をする際の保存要件は、下記の情報をご参照ください。
電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿書類関係】
JIIMA「電子帳簿ソフト法的要件認証」制度
公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(以下JIIMA)が、国税関係帳簿を作成・保存する市販ソフトウェアが法的要件を満たしていると判断したものを「電子帳簿ソフト法的要件認証」として認証しています。
本認証を受けたソフトウェアを利用することで、企業は経理業務の電子化を安心して進めやすくなります。
JIIMAの「電子帳簿ソフト法的要件認証」を取得したシステムのリストが、国税庁ホームページに掲載されています。
https://www.jiima.or.jp/certification/denshichoubo_soft/list/
JIIMA認証取得「SMILE」シリーズ

公益社団法人日本文書情報マネジメント協会
によりライセンスされています。
OSKの『SMILE V 2nd Edition 会計』『SMILE V Air 会計』は、電子帳簿保存法対応ソフトウェアの機能仕様の要件を満たしているとして、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)より認証を受けており、安心してご利用いただけます。
SMILEの機能をお試しいただける体験版をぜひご利用ください!
3. 事務手続きの明確化
帳簿作成に係る事務処理手続きを、各規程に定められている各条項等との整合性について検討して、業務フローの作成を行います。
2024年1月改正の概要
令和5年度 税制改正により、過少申告加算税の軽減措置の対象となる申告所得税および法人税に係る優良な電子帳簿の範囲が、下記に限定されました。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 以下の事項の記載に係る1.2.以外の帳簿
- 手形上の債権債務に関する事項
- 売掛金その他債権に関する事項
- 買掛金その他債務に関する事項
- 有価証券に関する事項※1
- 減価償却資産に関する事項
- 繰延資産に関する事項
- 売上その他収入に関する事項
- 仕入その他経費または費用に関する事項※2
- 申告所得税に係る優良な電子帳簿の場合は除く
- 法人税に係る優良な電子帳簿の場合は賃金、給料手当、法定福利費および厚生費を除く
電子帳簿保存法について、詳しく知りたい方はこちらの資料をぜひご覧ください!
関連する製品・サービスProduct / Service
製品お役立ち情報Contents
ご購入前の
製品/サービス
お問い合わせContact
企業のDX化や業務効率化に関するお悩みは「株式会社 OSK」へお気軽にご相談ください。